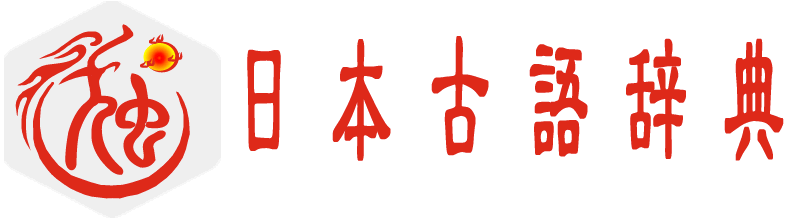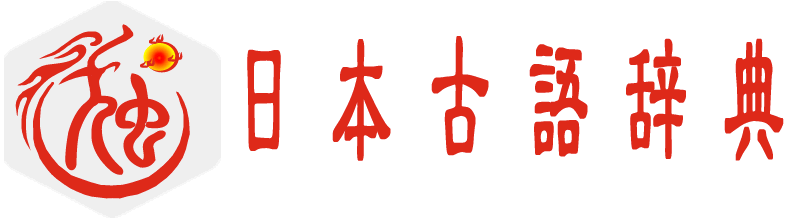つ 格助詞《接続》体言や形容詞の語幹に付く。〔所属・位置〕…の。…にある。▽連体修飾語を作る。 出典万葉集 三三「ささなみの国つ御神(みかみ)のうらさびて荒れたる京(みやこ)見れば悲しも」[訳] ささなみの国の神様の気持ちがすさんで荒れた古都を見ると悲しいことだ。◆上代語。 参考格助詞「の」に比較して、用法が狭く、中古以降は複合語の中で慣用的に用いられているだけである。「天(あま)つ風」「夕つ方」「先つ年」「まつげ(目つ毛)」「ときつ風」「たなばたつめ」 つ 助動詞 下二段型《接続》活用語の連用形に付く。(一)〔完了〕…た。…てしまう。…てしまった。出典竹取物語 かぐや姫の生ひ立ち「秋田、なよ竹のかぐや姫とつけつ」[訳] 秋田は、(かぐや姫に)なよ竹のかぐや姫と(いう名前を)付けた。(二)〔確述〕①〔「つ」が単独で用いられて〕必ず…する。間違いなく…てしまう。まさに…だ。出典徒然草 一〇四「門(かど)よくさしてよ。雨もぞ降る」[訳] 門をきっちり間違いなく閉めてしまいなさい。雨が降ったら大変だ。②〔「む」「らむ」「べし」など推量の助動詞を伴って〕きっと…(だろう)。間違いなく…(はずだ)。確かに…(したい)。出典枕草子 虫は「蠅(はへ)こそ、憎きもののうちに入れつべく」[訳] はえ(という虫)こそ、憎らしいものの中に確かに入れてしまいたいもので。(三)〔並列〕…たり…たり。▽「…つ…つ」の形で、動作が並行する意を表す。出典平家物語 三・足摺「僧都(そうづ)乗っては降りつ、降りては乗っつ、あらまし事をぞし給(たま)ひける」[訳] (俊寛)僧都は(船に)乗っては降りたり、降りては乗ったりして、乗って行きたいというようすをなさった。◇中世以降の用法。 語法(1)完了の助動詞 いわゆる完了の助動詞には「つ」「ぬ」「たり」「り」があるが、「つ」「ぬ」は過去・未来などの時間的関係を表す用法とは無関係に動作・作用の終了を表すのが基本の意味であり、「たり」「り」は存続の意味を基本とする。(2)「ぬ」との違い※右は、大体の傾向で、例外もある。 注意(二)の用法は、「てむ・つらむ・つべし」と推量の助動詞の上にあったら、「きっと…だろう」と訳してみる。「確述」は強意とも呼ばれる。 付け句 分類文芸連歌(れんが)・俳諧(はいかい)で、すでに示されている前句(まえく)に付けるあとの句。 付け合い 分類文芸連歌(れんが)・俳諧(はいかい)で、すでに示されている句に対して、それに応じる句を付けること。すでに示されている句を「前句(まえく)」、それに付ける句を「付け句」という。五・七・五の長句には七・七の短句を付け、短句には長句を付ける。付け合いの種類には、前句の言葉や意を汲(く)んで付ける「心付け」、前句の言葉や物に関連して付ける「物付け」、前句の余情を汲んで付ける「匂(にお)い付け」などがある。 つ 【津】 名詞船着き場。港。渡し場。 津の国 分類地名「摂津(せつつ)」の国の古名。 |