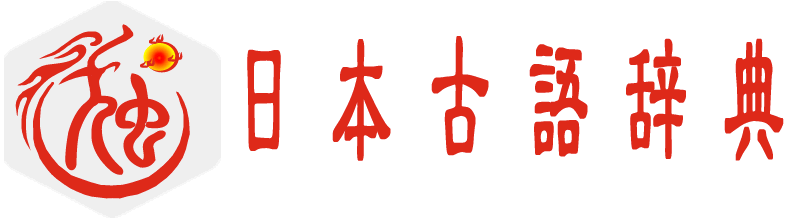の 格助詞《接続》体言や体言に準ずる語に付く。 ①〔連体格=連体修飾語をつくる〕(ア)〔所有〕…の。…がもっている。…のものである。出典万葉集 一四七「大君の御寿(みいのち)は長く天(あめ)足らしたり」[訳] 天皇のご寿命は長く空に満ち満ちていらっしゃった。(イ)〔所属〕…の。…に属する。…のうちの。出典徒然草 五三「仁和(にんな)寺の法師」[訳] 仁和寺に属する法師。(ウ)〔所在〕…の。…にある。出典万葉集 七「宇治(うぢ)のみやこの仮盧(かりいほ)し思ほゆ」[訳] 宇治の都にある仮(かり)の小屋が思い出される。(エ)〔時〕…の。出典土佐日記 一二・二一「県(あがた)の四年五年(よとせいつとせ)果てて」[訳] 地方官としての勤務期間の四、五年の任期が終わって。(オ)〔作者・行為者〕…の。…の作った。…のした。出典源氏物語 桐壺「人の謗(そし)りをもえはばからせ給(たま)はず」[訳] (帝(みかど)は、世間の)人の非難などにも気がねなさることもなくて。(カ)〔材料〕…の。出典万葉集 三五六七「置きて行かば妹(いも)ばまかなし持ちて行く梓(あづさ)の弓の弓束(ゆつか)にもがも」[訳] 置いて行ったら、妻はかわいそうだ。持って行く梓の弓の握るところであればよいのに。(キ)〔名称・資格〕…の。…という。出典竹取物語 ふじの山「その山をふじの山とは名づけける」[訳] その山を(士(つわもの)に富む山の意で)富士の山と名付けたのである。(ク)〔様子・状態〕下に「ごとし」「やうなり」「まにまに」「からに」「ゆゑに」などを伴う。出典伊勢物語 二三「つひに本意(ほい)のごとくにあひにけり」[訳] とうとう、かねての望みのとおりに結婚したのだった。②〔主語を示す〕…が。出典枕草子 春はあけぼの「まいて雁(かり)などの連ねたるが、いと小さく見ゆるは」[訳] いうまでもなく雁などが連なって(飛んで)いるのが、とても小さく見えるのは。③〔同格〕(ア)〔同様の体言を前後に伴って〕…であって(しかも)。…でまた。出典万葉集 八九二「風交じり雨降る夜(よ)の雨交じり雪降る夜よは」[訳] ⇒かぜまじり…。(イ)〔下の体言を省略して〕…であって(しかも)。出典伊勢物語 九「白き鳥の、嘴(はし)と脚と赤き、鴫(しぎ)の大きさなる」[訳] 白い鳥であって、くちばしと脚とが赤い鳥で、鴫くらいの大きさの(鳥)。◇「赤き」「大きさなる」の次に「鳥」が省略されている。④〔(下の体言を省略して)体言の意味を含んだ働き〕…のもの。…のこと。出典枕草子 中納言まゐり給ひて「まことにかばかりのは見えざりつ」[訳] 本当にこれほどのもの(=見事な扇の骨)は、目にしたことがなかった。⑤〔連用格=連用修飾語をつくる〕(ア)〔比喩〕…のように。出典万葉集 二一「紫草(むらさき)の匂(にほ)へる妹(いも)を憎くあらば人妻ゆゑに我恋ひめやも」[訳] ⇒むらさきのにほへるいもを…。(イ)〔動作の目的・対象〕…を。出典源氏物語 桐壺「見てはうち笑(え)まれぬべきさまのし給(たま)へれば」[訳] 見てほほえまずにはいられないようすを(若宮は)していらっしゃるので。⑥〔並列〕…だの。…とか。出典浮世風呂 滑稽「着物がきたねの、貧乏人だのと」[訳] 着物が汚いだの、貧乏人だのと。◇中世以降の用法。 語法(1)主語を示す用法②の用法は「…の…連体形+が」「…の…連体形+は」の形になることが多い。また、主語を受ける述語は連体形になる。(2)「…の…さ」の用法 「の」+形容詞語幹+接尾語「さ」の形の場合、全体で詠嘆を表す。「…が…であることよ」などと訳すとよい。「月の影のさやけさ」(『新古今和歌集』)〈月の光がなんと澄んでいることよ。〉 参考①(ク)は、「まにまに」の「ま」などが体言に由来する語なので、連体格とする。④の「の」を準体助詞、⑥の「の」を並立助詞とする説がある。 の 終助詞《接続》体言や、文を言いきった形に付く。…だなあ。…だね。▽感動や念押し・同意などの意を表す。出典浮世風呂 滑稽「はて、とんだ物が目にはいったの」[訳] それにしても、とんでもない物が目に入ったなあ。◆中世以降の用法。 の 【篦】 名詞矢の竹でできた部分。矢柄(やがら)。 の 【野】 名詞草や低木が生えている広い平地。 野ざらし紀行 分類書名俳諧(はいかい)紀行。松尾芭蕉(ばしよう)作。江戸時代前期(一六八五)成立。一巻。『甲子(かつし)吟行』ともいう。〔内容〕芭蕉紀行の第一作で、貞享(じようきよう)一年(一六八四)八月江戸を出発して、故郷の伊賀(いが)で年を越し、翌年四月江戸に帰るまでの俳文的紀行である。 |