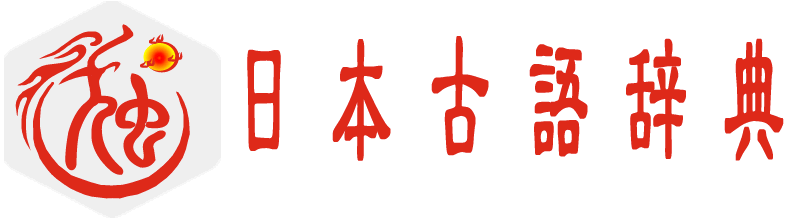きは 【際】 名詞① (物の)端。へり。出典源氏物語 夕顔「母屋(もや)のきはに立てたる屛風(びやうぶ)」[訳] 母屋の部屋の端に立ててある屛風。②(物と物との)境目。仕切り。出典源氏物語 末摘花「二間(ふたま)のきはなる障子(さうじ)」[訳] 二間の部屋の境目にある障子。③わき。そば。出典徒然草 四一「おのおの下りて、埒(らち)のきはに寄りたれど」[訳] (賀茂(かも)の競(くら)べ馬を見ようと)それぞれ(車から)降りて、馬場の柵(さく)のそばに寄ったけれども。④分(ぶん)。▽ある限られた範囲のもの。出典枕草子 職の御曹司におはします頃、西の廂にて「はじめのきはをおきて、今のはかき捨てよ」[訳] (雪の)初めに降った分だけ残して、今(新しく降った)のは払い捨てなさい。⑤身分。家柄。身の程。分際。出典源氏物語 桐壺「いとやむごとなききはにはあらぬが、すぐれて時めき給(たま)ふありけり」[訳] それほど高貴な身分ではない方で、際だって帝(みかど)のご寵愛(ちようあい)を受けて栄えていらっしゃる方があった。⑥(物事の)限り。限界。出典枕草子 位こそ猶めでたき物はあれ「受領(ずりやう)の北の方にて国へ下るをこそは、よろしき人の幸ひのきはと思ひて、めでうらやむめれ」[訳] 国司の奥方となって任国に下るのを、これこそ普通の女の幸福の限りと思って、すばらしく思いうらやむようだ。⑦程度。出典徒然草 五九「人を見るに、少し心あるきはは、皆このあらましにてぞ一期(いちご)は過ぐめる」[訳] (世間の)人を見ると、少々分別がある程度(の人)は、皆この(出家の)計画をするだけで、一生は過ぎてしまうようだ。⑧時。場合。折。当座。出典徒然草 三〇「そのきはばかりは覚えぬにや、よしなし事言ひてうちも笑ひぬ」[訳] (人が死んでも、死んだ)その当座ほどは感じないのだろうか、つまらないことを言って、つい笑ってしまったりする。⑨決算期。支払い日。▽江戸時代、年末・盆など節季の前。出典女殺油地獄 浄瑠・近松「互ひに忙しいきはの夜さ、ここへはなんの用がある」[訳] お互いに忙しい(節季の前の)支払い日の夜に、ここにはなんの用がある。◇近世語。 きわ 【際】 ⇒きは |