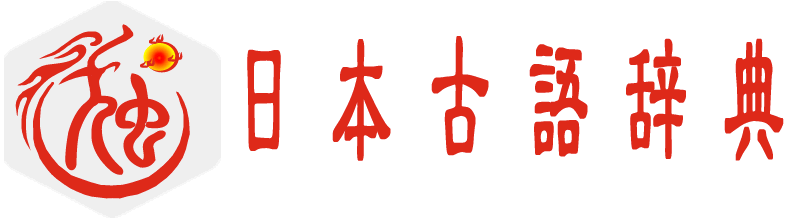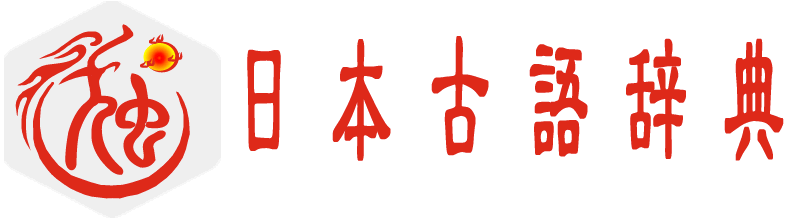な-・む 分類連語 ①…てしまおう。必ず…しよう。▽強い意志を表す。出典土佐日記 一二・二七「『潮満ちぬ。風も吹きぬべし』と騒げば、船に乗りなむとす」[訳] 「潮も満ちた。風もきっと吹くだろう」と騒ぐので、船に乗ってしまおうとする。②…てしまうだろう。きっと…するだろう。確かに…だろう。▽強い推量を表す。出典更級日記 物語「盛りにならば、形も限りなくよく、髪もいみじく長くなりなむ」[訳] (私も)年ごろになったならば、顔かたちもこの上なく美しく、きっと髪もすばらしく長くなるだろう。③…ことができるだろう。…できそうだ。▽実現の可能性を推量する。出典徒然草 一〇九「かばかりになりては、飛び降(お)るるとも降りなん」[訳] これくらい(の高さ)になったからには、飛び降りても降りることができるだろう。④…するのがきっとよい。…ほうがよい。…すべきだ。▽適当・当然の意を強調する。出典徒然草 六「子といふもの、なくてありなん」[訳] 子供というものは、ないほうがよい。⑤〔係助詞「や」を伴って〕(ア)…するつもりはないか。…てくれないか。▽相手の意向を問う。出典源氏物語 桐壺「忍びては参り給(たま)ひなむや」[訳] ひそかに参内(さんだい)しなさってくださいませんか。(イ)…できるだろうか、いや…できないだろう。▽反語の意を表す。出典竹取物語 御門の求婚「国王の仰せ言(ごと)を、…承り給はでありなむや」[訳] 国王のご命令を、…お受け申し上げなさらないでいられましょうか、いや、いられないだろう。 参考活用語の連用形に接続する連語。「なん」とも表記される。 なりたち完了(確述)の助動詞「ぬ」の未然形+推量の助動詞「む」 なむ 助動詞 特殊型《接続》活用語の終止形に付く。活用{○/○/なむ/なむ/なめ/○}〔現在推量〕…ているだろう。出典万葉集 三三六六「鎌倉の美奈(みな)の瀬川に潮満つなむか」[訳] 鎌倉の美奈の瀬川に潮は満ちているだろうか。◆上代の東国方言。助動詞「らむ」に相当する。 なむ 係助詞《接続》体言、活用語の連体形、副詞、助詞などに付く。連用修飾語に付くときは連用形に付く。①〔強意〕文中に用いられて、その付いた上の語句を強調する。文末の活用語は連体形で結ぶ。出典竹取物語 かぐや姫の生ひ立ち「その竹の中に、もと光る竹なむ一筋ありける」[訳] その竹の中で、なんと根もとが光る竹が一本あった。②〔余情〕「なむ」を受ける結びの「ある」「言ふ」「侍(はべ)る」などを省略した形で余情を表す。出典源氏物語 桐壺「かかる仰せごとにつけても、かきくらす乱り心地になむ」[訳] このようなお言葉につけても、心が暗み取り乱した気持ちでございますよ。 語法(1)係り結び (結びは連体形)(2)結びの省略 「なむ」を受けて結びとなるはずの語句が省略されて、「なむ」で言い切った形になることもある。たとえば②の例では「なむ」の下に連体形「侍(はべ)る」が省略されている。(3)結びの消滅 「なむ」を受ける結びの部分に接続助詞が付いて下に続く場合、結びは消滅する。たとえば「年ごろよく比べつる人々なむ別れがたく思ひて」(『土佐日記』)〈この数年来親しく付き合ってきた人々は特別に別れがたく思って。〉では「なむ」を受けて連体形「思ふ」となるところだが、下に接続助詞「て」が付くため、連用形「思ひ」となって、結びが消滅する。 参考上代には「なも」という語もあったが、『万葉集』ではすでに「なむ」を多用。中古には、会話文・手紙文に多用され、中古末には衰退し始めた。「なん」とも表記される。 なむ 終助詞《接続》活用語の未然形に付く。〔他に対する願望〕…てほしい。…てもらいたい。出典更級日記 梅の立枝「いつしか梅咲かなむ」[訳] 早く梅が咲いてほしい。 参考上代には「なむ」と同じ意味で「なも」を用いた。「なん」とも表記される。⇒表組。 なむ 【南無】 名詞信仰する仏・菩薩(ぼさつ)・教えなどの上に付けて、それらに心から帰依する気持ちを表す語。「なも」とも。◆仏教語。 な・む 【並む】 >[一]自動詞 マ行四段活用活用{ま/み/む/む/め/め}並ぶ。連なる。出典万葉集 四三七五「松の木のなみたる見れば」[訳] 松の木が並んでいるのを見ると。 >[二]他動詞 マ行四段活用活用{ま/み/む/む/め/め}並べる。連ねる。出典万葉集 四三一〇「石なみ置かば継ぎて見むかも」[訳] (天の川に)石を並べて置いたなら(牽牛(けんぎゆう)と織女は)絶えず会うことができるだろうかなあ。 >[三]他動詞 マ行下二段活用活用{め/め/む/むる/むれ/めよ} >[二]に同じ。出典古今集 春上「駒(こま)なめていざ見に行かむ故里(ふるさと)は雪とのみこそ花は散るらめ」[訳] 馬を並べて、さあ見に行こう。あの懐かしい土地では、まるで雪のように桜が散っているだろう。 |